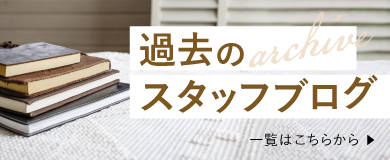私が蓼科にやってきたのは、1993年の夏だった。
平成になって5年目のこと。
あれから、もう32年が経つ。
その年の日本は、冷たかった。
田んぼの稲が育たず、スーパーからお米が消えていった。
日本中が、「まさかの米がない」という年だった。
思い返せば、私はあのとき、
はじめてタイ米を買った。
タイには行ったことがあったが、タイ米を美味しく炊くことはできなかった。
蓼科の夏も、その年は寒かった。
標高1,500メートルにあるマンションの管理人として住んでいた山小屋風の山荘では、
「暖房をつけたい」と思うほどの涼しさだった。
8月なのに、ストーブを点けた。
蓼科の夏って、こういうものなんだと思った。
でも、私はこの場所が気に入った。
空気のうすさも、夜の静けさも。
どこか、人の暮らしを遠くから見守っているような、そんな山の雰囲気に惹かれてしまったんだと思う。
それからというもの、
気がつけば私はここで、
二人の娘を育てながら、生活の場所として、仕事場として、住み続けることになった。
季節の移ろいと、木々のざわめきと、
そして、いろんな人たちの「人生の一部」と出会いながら。
ある日の夜中、「ごめん、明日のゴルフ代が足らないんだ。ちょっと貸してくれない?」
そんなお客さんがいた。
その人もきっと、蓼科が好きだったんだろう。
きっとここでは、よく眠れたんだと思う。
まだパソコンもスマホもない、のんびりした、アナログな時代だった。
休みの日には、子どもと一緒に公園へ行ったり、家族で県内の温泉を巡ったりした。
蕎麦も食べた。地ビールもよく飲んだ。
佐久にある「ほのかの湯」という地元の温泉に行った時のこと。
シャンプーが置いておらず困っていたら、隣のおじさんが「使いなよ」と貸してくれた。
脱衣所で服を着ていたときには、私の襟をそっと直してくれた。
そんなこと、なかなかない。今でもよく覚えている。
また行きたい、あの温泉。
平成の時代には、いろんなことがあった。
事件も、災害も、不景気も。
でも、蓼科の森は変わらなかった。
雨の日は雨の音が、雪の日は雪の静けさが、あった。
あの冷たい夏から、もう32年。
私の中には、あのときつけたストーブの炎のゆらぎが、今でも少し残っている。
そして最近、大好きだった二人が逝ってしまった。
大相撲の解説の北の富士さん。自由なトークが好きだった。
「にっぽん縦断 こころ旅」の日野正平さん。おもねらない生き方が、かっこよかった。
ほんとうに、残念だった。
…てなことを共有できる人が、いなくなったな〜と、しみじみ思います。
以上、自由勝手な文章にお付き合いいただき、ありがとうございました。(和)